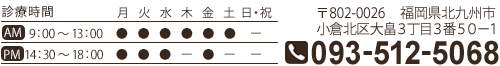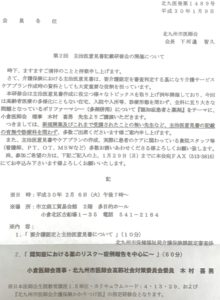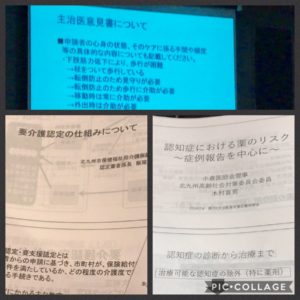北九州市小倉北区でのC型肝炎、肝臓癌、肝炎、肝硬変などの治療は医療法人さがら内科クリニックへ。
📓〜主治医意見書記載研修会〜📓
昨日(2/6)は市商工貿易会館にて主治医意見書記載研修会が行われました。
会では、主治医意見書への記載注意点や、主治医への情報提供対象拡大等々の申し合わせなどありましたが、講演で小倉医師会理事の木村喜男先生より『認知症における薬のリスク』というお話がありました。
認知症の診断には画一的なものはなく、患者家族や介護されてる周りのお話が非常に重要となるのですが、“急に言動がおかしくなった”、“認知がひどくなった”などのとき、常用している薬剤を今一度見直すことも診断の一助になる。
特に認知症関連では認知症の増悪原因と思われる薬剤を休薬することだけで症状が改善することが多々あるという内容でした。
いつも私どもは自分たちの処方には気をつけているつもりではありますが、漫然とした中には留意せざる薬剤がないわけではありませんし、他(院)科で処方されている薬剤まではわからないこともあります。
特に、睡眠導入剤や安定剤、抗うつ(精神)剤などは留意要すことはよく知られてますが、胃薬でのH2ブロッカーや抗アレルギー薬のヒスタミン製剤や、抗パーキンソン薬、排尿障害等での抗コリン製剤、降圧(不整脈)剤の一部、抗甲状腺薬などなど留意要す薬剤は多岐にわたりますが、最近話題の高齢者の“ポリファーマシー(多剤服用)”にも関わることなので、我々実地医家としても十分気をつけて診療する必要性があることを改めて認識した次第でした。
木村喜男先生ご講演お疲れ様でした。
来週13日には私が認知症サポーター医として『認知症かかりつけ医研修会』診断・治療のお話をしなければなりませんので、大変参考になりました。
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.